今田人形座 [外題の紹介]
ページID:0000712 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月18日更新

今田人形は現在、十一外題を演じます。
江戸時代から明治時代に作られた、武勇伝の流れをひく時代物と、身近な町人の事件を描く世話物の名作が、
喜怒哀楽を大胆に、心のひだまでしっとりと写し出し、いまも、みる人の心をひきつけます。
異色の演目は昭和の今田人形オリジナル作品「小太郎物語」です。どの出し物も、リアルで、こまやかな技が、心の琴線にふれる世界を描き出します。
| 寿式三番叟 (ことぶきしきさんばそう) | 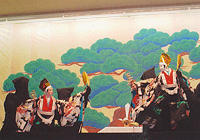 | 天下太平、五穀豊穣を祈願するご祝儀の舞です。 能の『翁』(おきな)と、狂言方が舞う『三番叟』を義太夫節にしたこの舞は、 謡曲の節のおもむきがその底に流れています。 今田人形の三番叟は翁、千歳が祝い浄めて舞台を去ったあとに登場する 二人の三番叟の、『揉の段』につづく後半部分の『鈴の段』だけをアレンジして舞います。 三番叟は、まず、四隅と中央の五方をきよめ、 柝、太鼓、鼓、笛の囃子と三味線、太夫の語りにのってにぎやかに舞います。 やがて鈴を持って四方に種を蒔くころから舞がだんだん早くなり疲れて休む三番叟。 それを無理やり立たせる三番叟。 華やかにユーモラスに、最後は揃ってめでたく舞い納めます。 |
|---|---|---|
| 戎舞 (えびすまい) |  | 乾の方角から烏帽子をかぶり、狩衣を着た戎様が 釣り竿をかついで庄屋さんの家にやってきました。 庄屋さんは家を清め御神酒を出します。 三ごんの杯を飲み干した戎様は、福の神であることを話しながら舞いはじめ…。 酔った戎様は舟に乗り大きな鯛を釣り、めでたし、めでたしと舞い納めます。 |
| 絵本太功記 (えほんたいこうき) 十段目 尼ヶ崎の段 | 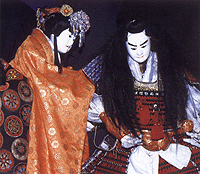 | 絵本太功記は「本能寺の変」前後の武智(明智)光秀主役の物語です。 十段目尼ヶ崎の段は「太十」とよんで親しまれている全編のクライマックスです。 光秀の老母さつきの住まい尼ヶ崎で光秀の一子十次郎の婚約者初菊との祝言。 一夜の宿をとった旅の僧、実は真柴久吉(豊臣秀吉)を刺すつもりで 母を刺してしまう光秀。 重傷を負って初陣から戻る十次郎。久吉につめよる光秀。 それを押しとめて孫十次郎とともに息絶えるさつき。光秀の妻操と初菊の嘆き。 そして光秀と久吉の対面。 息もつかせない時代物浄瑠璃の醍醐味を満載したお芝居です。 写真は初菊のくどきで「痛わしや十次郎様…」と泣き崩れる、悲しく哀れな場面です。 |
伽羅先代萩 |  | 奥州伊達藩のお家騒動の物語で、天明五年に江戸の結城座で初演されました。 伊達藩は故あって幼い鶴喜代(つるきよ)があとをついでいます。 この鶴喜代を殺して藩を乗っ取ろうという悪だくみがすすんでいます。 鶴喜代の乳母政岡は暗殺を心配して自分で炊いたご飯しか食べさせません。 悪人の八汐(やしお)は政岡を鶴喜代のそばから離そうとします。 頼朝の使いといって、栄御前があやしい菓子折りを持ってきて、 鶴喜代に無理に食べさせようとします。 政岡の子千松が駆け込んできて食べ、苦しみだします。 悪事を隠そうと、八汐は千松を残忍に刺し殺します。 写真は千松を刺す八汐。 |
| 菅原伝授手習鑑 (すがわらでんじゅ てならいかがみ) 寺子屋の段 | 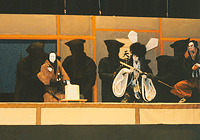 | 浄瑠璃三代傑作の一つ、時代物です。 菅原道真を流罪に追い込んだ藤原時平は、 道真の子、管秀才までも殺そうとしています。 武部源蔵はかくまっている秀才の首を差し出すように命じられて寺子屋に帰り、 留守中に預かった小太郎を見て一大決心をします。 そこへ時平の家来、検使の玄蕃と首実検役の松王丸が首を受け取りに来ます。 首実検が始まります。息を詰める源蔵と妻戸浪。玄蕃も刀に手をかけてにらみます。 秀才の首に間違いないと認め、松王丸と玄蕃は去ります。 そこへ小太郎の母千代とやがて忍び姿の松王丸も戻ってきます。 実は小太郎は秀才の身代わりにあずけた松王丸の息子だったのです……。 写真は松王丸と千代。 |
| 壺坂霊験記 (つぼさかれいげんき) 沢市内より 御寺まで |  | これは明治二十年に二世豊沢団平がそれまでのものを直して上演した作品です。 壺坂寺の近くで、疱瘡で目が見えなくなった沢市が琴や三味線を弾きながら、 妻お里の賃仕事を頼りに細々と暮らしていました。 ある日、沢市は毎晩お里がいなくなるのが苦になって、 三味線で紛らせているというのです。 驚いたお里ははじめて、 沢市の目が治るように壺坂の観世音へ三年越しでお参りしているのだと打ち明けます。 これを聞いて沢市は詫び、お里と一緒にお参りに出かけます。 しかし、沢市はお里がいない間に谷に飛び込みます。 それを知ったお里も身を投げます。すると観世音が現れたのです…。 写真はお里が「観音様へ来たわいナァ」と沢市に。 |
| 傾城阿波の鳴門 (けいせいあわのなると) 巡礼歌の段 |  | 近松門左衛門の原作を改作して、 お家騒動を絡ませた十段つづきで明和五年の初演です。 現在は八段目「十郎兵衛住家」だけが上演されます。「巡礼歌の段」はその前半です。 阿波十郎兵衛は主家の宝、国次の刀を探して 盗賊銀十郎となって大坂に住んでいます。 女房お弓が一人留守番をしているところへ 幼いおつるが父母をさがして「巡礼に御報謝」と訪ねてきます。 お弓は話を聞いて実の娘と気づきますが、 名のってはかえっておつるに難儀がかかると、髪を直して帰らせます。 しかし、思い返してあとを追うのでした。 写真は、「とと様の名は阿波の十郎兵衛、かか様の名はお弓ともうします」という おつるの声を聞いて、思わず抱きしめようとするお弓。 |
| 生写朝顔話 (しょううつしあさがおばなし) 宿屋より大井川 | 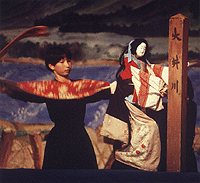 | 天保三年に初演された五段続きの時代物です。 宇治の蛍狩りでたがいに見初めた宮崎阿曽次郎と家老の娘深雪の悲しい恋の物語です。 伯父の家を継いで駒沢次郎左衛門は島田宿で、変わり果てた盲目の深雪に会います。 しかし、同道の岩代多喜太のてまえ名乗ることも出来ず、 目薬と金子(きんず)を宿の亭主戎屋徳右衛門に託して去ります。 宿を下がった深雪もなぜか気になって引き返し、 やはり恋人だったと知ってあとを追います。 大井川に恋人の姿はなく、急な大水で川止めです。 深雪は天を恨み、わが身を恨んで川に身を投げようとします。が…。 |
| 伊達娘恋緋鹿子 (だてむすめこいのひかのこ) 火の見櫓の段 |  | 八百屋お七を題材にした八段つづきの世話物で安永二年に初演されました。 いまは六段目の「八百屋」だけが残り、 しかもほとんど「火の見櫓」の部分の上演となっています。 お七は相思相愛の小姓吉三郎から、 探している剣を今夜中に取り戻さなければ死ぬという遺書を渡されます。 その後で、お七に横恋慕の武兵衛が待っていることを突き止め、 下女お杉が取り返してくるのを待っています。 夜中の十二時の鐘が鳴りました。町の門が閉められます。 門をあけるには半鐘を打って火事だと思わせるしかありません。 火事でもないのに半鐘を鳴らせば火あぶりの刑です。 しかし七は吉三郎のために火の見櫓に登ります。この、櫓を登るところが驚きです。 |
| 日高川入相花王 (ひだかがわいりあいざくら) 渡し場の段 |  | 安珍、清姫の道成寺伝説に皇位継承権の争いを絡めた五段つづきで、 宝暦九年の初演です。 朱雀天皇が弟の桜木親王に皇位を譲ろうとしますが、 反対派が親王の命を狙っています。 親王は安珍と名をかえて逃れ、熊野の真那古庄司の館にたどり着き、 恋人と再会します。 ところが庄司の娘清姫が親王とも知らず安珍を恋していたのです。 嫉妬に狂った清姫は安珍のあとを追います。 月明かりの中、道成寺に近い日高川にたどり着いた清姫は船頭を呼びますが、 安珍に金をもらって川を渡さないよう頼まれている船頭は、清姫を冷たくあしらいます。 どうしても安珍に追いつきたい執念で清姫は大蛇になって川を渡ってゆくのです。 |
小太郎物語 |  | 飯田市の市民手づくりの今田人形オリジナル作品で、昭和五十八年の初演です。 浄瑠璃が分からない子どもたちにも楽しい今田人形にふれて欲しいと願って、 長野県の民話を素材に、ふるさとことばや、子どもも歌える歌がちりばめられています。 十歳になった小太郎は、欅のおじいまや隣のゆうに助けられて、 お腹の小太郎のためによその畑のものを食べて竜にされた母親を探しに出かけます。 暗い湖で白竜の母に出会った小太郎は親子で山を砕き、水を抜いて田畑を広げます。 小太郎を乗せて空高く舞い上がった母竜は、地上に降りて天の竜の川になり、 人の姿に蘇ります。 ようやく一緒になれた小太郎と母は龍江の里で楽しく暮らします。 |
東海道中膝栗毛 |  | 江戸時代のベストセラー。十辺舎一九の滑稽本「東海道中膝栗毛」を題材としたもの。 江戸に住む弥次郎兵衛と喜多八が伊勢詣りの為、東海道を旅する。 三河の御油の宿を出た二人は、悪い狐が出る噂の場所を通りかかります。 墓場の近くで親父と子供に出会い、化け物と早合点。 又、和尚に会ったりユーモアたっぷりのやりとりがみられます。 |

