立石寺木造天部形立像
立石寺木造天部形立像(りっしゃくじもくぞうてんぶぎょうりゅうぞう) 1体
区 分:飯田市有形文化財(令和3年3月12日 指定)
所在地:立石140番地 立石寺
所有者:立石寺
年 代:10世紀後半(平安時代中期)
規模等:像高95.1cm、カツラ一木造(いちぼくづくり ※1)、内刳り(うちぐり ※2)、彫眼(ちょうがん ※3)
※1 一木造:平安時代初期の彫刻技法で、像全体から台座まで1本の木材から彫り出す技法です。のちに一木造の基本的条件は、頭部と体部が一材から彫り出されることとし、体部から離れている手足やその他の小部分などが別材であっても一木造りと考えるようになりました。
※2 内刳り:乾燥によるひび割れを防ぐために、像の内部を刳り抜くことです。
※3 彫眼:像の表面をじかに彫って表現された目のことです。

概 要:
頭部には山形の冠をつけ、髪を頭の上で束ねています。側頭部の髪は炎のように逆立ち、顔は目を怒らせて口を結んだ憤怒(ふんぬ)の形相を表しています。
体には唐風の甲(よろい)を着て、沓(くつ)を履き、邪鬼を踏みつけて立っています。
両肩から先の腕は後世に修理されていますが、左腕の臂(ひじ)から先を失っており、手に何を持っていたのか分かりません。しかし、立石寺に伝わる他の天部像(※4)の様子から、四天王(※5)像の内の広目天(※6)像とみられます。鎌倉時代の四天王像に比べると激しい動きや写実性はありません。
この像は、立石寺の秘仏である木造十一面観音立像(長野県宝)と同じ種類の木を材料としていたり、節があるような木を使っていたり、内刳りが無く、衣や甲の彫りが浅い点などがよく似ています。作られた時代は双方とも10世紀後半で、作者も同じかもしれません。
なお、残る増長天・持国天・多聞天は制作年代が異なっています。恐らく、仏像が壊れたりしたため、新しく作り直されたのでしょう。
※4 天部像(てんぶぞう):仏法の守護神の像、四天王や十二神将、帝釈天などのことです。
※5 四天王(してんのう)、※6 広目天(こうもくてん):四天王とは、持国天・増長天・広目天・多聞天の四神のことです。持国天は東、増長天は南、広目天は西、多聞天は北を守護します。
主な部位の名称:
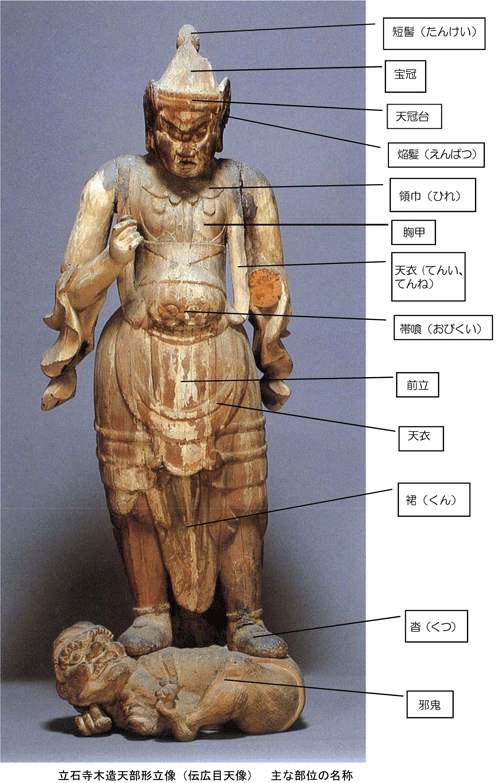
「立石寺木造天部形立像」の価値:
(1)県内最古級の神将形天部像であること
神将像(しんしょうぞう)とは甲冑を身に着けた仏像のことです。
平安時代中期に遡る神将形天部像は県内でも最古級で、類例の少ない貴重な仏像です。
(2)当地域に本格的な仏教文化が平安時代に浸透したことを伝える仏像の一つであること
平安時代には天台宗や真言宗が急速に地方に広がっていきますが、その動きの中で当地域にも本格的な仏教文化が浸透していったことを伝えている仏像の一つです。

