天龍峡碑
ページID:0126088 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月20日更新
天龍峡第二公園内の川岸寄りの一段高い小山の上に、天龍峡を命名した経過を記した天龍峡碑が建てられています。
 高さ約4.2m、幅約0.9m
高さ約4.2m、幅約0.9m
天龍峡碑は小山のさらに一段高い位置にあり、現地で碑文を読みにくいほどの場所ですが、天竜川の対岸から見るとその存在感に気付かされます。
江戸時代の弘化4年(1847)、学友である飯田藩出身の丸山仲肅を訪ねた阪谷朗廬(さかたにろうろ)は、関島松泉(下川路村郷医・文人)の案内で、まだ無名の天龍峡を訪れました。関島松泉との文学談義の中で峡谷が未命名であることを知ると、これを「天龍峡」と命名し、峡谷を賛美した『遊天龍峡記』を残しました。
文中で阪谷朗廬は、峡谷の深く険しい姿とその間を流れ下る天竜川の激流を詠(よ)み、峡谷内の木々や、水の青さをたたえ、峡谷から見上げた空を川の流れに対比させ、その美しさを述べています。また、ツツジの赤い花が崖面に点在する様や、老松を頂く龍角峯の雄大さを描写しています。天龍峡記は文学的にも優れており、峡谷美を世に知らしめた最初の作品でもあります。

阪谷朗廬(1822~1881)
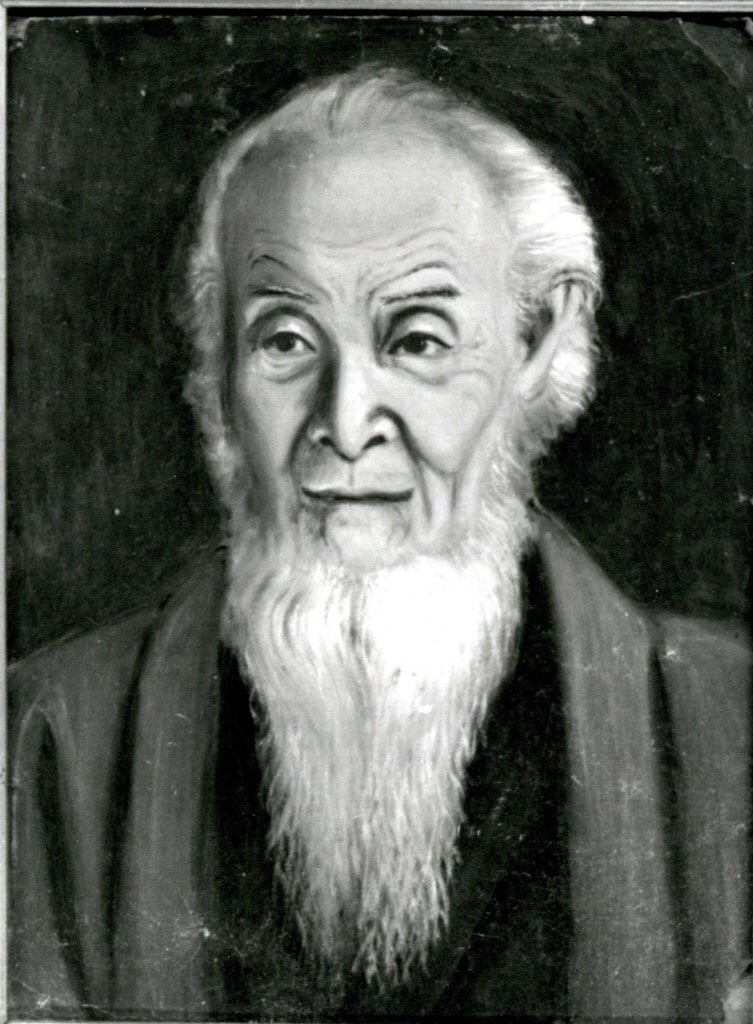
関島松泉(1806~1888)

